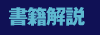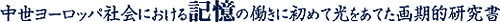記憶術と書物[詳細]
The Book of Memory
人間がもつ創造的能力のうちで最高のものは何か。
現代人ならだれもが「想像力」をあげるだろう。
ところが中世ヨーロッパでは「記憶力」こそが、人間の最も偉大な能力だった。
当時、多くの書物は図書館に収められ、
人々はもっぱら書物を記憶することで学問を収めなければならなかった。
そのためにさまざまな記憶術が考案され、教育されていった。
そして、書物の体裁やレイアウトも、
テクストをより記憶しやすいように工夫された。
書物は「記録のための道具」ではなく、「記憶のための道具」だった!
■目次より |
▲ |
記憶力と想像力の地位
トマス・アクイナスの記憶力
記憶のテクニック
書く能力は記憶力を低下させたか?
中世の記憶術へのアプローチ
第1章 記憶の諸モデル
「目で見るもの」としての記憶
「記憶=蝋引き板」モデル
言語による表象のとらえ方
記憶術のシステム
「記憶=貯蔵室」モデル
「蜜蜂」「鳥」の比喩
「小銭入れ」「保管所」の比喩
「箱」の比喩
第2章 記憶の神経心理学的解釈
記憶を作り出す内的感覚の働き
記憶とイメージ
知覚認識に身体はいかに関わるか?
記憶イメージの形成のされ方
想起のシステム
記憶と人間の性向
建築的記憶術
ソヴィエトの記憶家Sの記憶技法
第3章 初歩の記憶法
番号グリッドによる記憶術
「分割」と「組み立て」の効用
意味単位に従う記憶
聖書における章と節の分化
記憶用座標としての出典表示
「しるし」による整理収納
記憶における「しるし」の価値
テーマ別用語索引システム
第4章 記憶術
建築的記憶術の復活
記憶を補助する動物寓話集
記憶術における「場所」
奇異な「イメージ」の配置
鮮明な「イメージ」の配置
記憶術の中世的特色
「内容の表象」の重要性
学術としての記憶術の再評価
第5章 記憶と読書の倫理
口伝による情報の伝達
訓練された記憶と書物
消化瞑想活動としての読書
記憶共有体験としての読書
音読と黙読の機能の相違
記憶に関わる詞華集の役割
倫理的素養を育てる記憶
中世の読書の本来の姿
第6章 記憶と権威
著述と読書の補完関係
記憶による著述の諸段階
記憶の中から草稿を生み出す方法
頭の中で草稿を作り上げる方法
記憶術的な著述の構成例
テクストの書き込み=「権威」の獲得
注釈書の記憶用レイアウト
真の模倣と偽の模倣
第7章 記憶と書物
テクストに含まれる絵とことば
写本の装飾に込められた意味
箱船に関するフーゴーの記憶図表
箱船全体の構造設計
本のレイアウトと記憶効果
絵入り図表・輪形図表の機能
写本の装飾の実利的効用
付録A サン・ヴィクトルのフーゴー「しるしに関わる三つの大きな条件について」
付録B アルベルトゥス・マグヌス『善について』第4論考第2問「賢慮の諸部分について」
付録C トマス・ブラドウォーディン「人為的記憶について」
■関連図書 |
▲ |
[1] 論理学 10000円
[2] 数学論・数学 12000円
[3] 数学・自然学 17000円
[4] 認識論[人間知性新論…上] 8500円
[5] 認識論[人間知性新論…下] 9500円
[6] 宗教哲学[弁神論…上] 8253円
[7] 宗教哲学[弁神論…下] 8200円
[8] 前期哲学 9000円
[9] 後期哲学 9500円
[10] 中国学・地質学・普遍学 8500円
■書評 |
▲ |
◎松岡正剛氏(千夜千冊・遊蕩篇1314夜 2009.8.18)
読むとは、記憶を動かすことである。記憶するとは、自然や社会や出来事や思考や心情を、「読めるようにしておく」ということである。そのように記憶と読書が対応するように中世の書物はつくられ、その書物が活用されてきた。書くことと読むことは、同じ作用だったのだ。そこには、読み書き両用の編集法と用語法と注意法がつねに用意されていた。それを基礎付けているのが記憶術である。記憶と書物をめぐるアルス・コンビナトリアは、IT検索社会の今日こそ、勇躍、蘇るべきだろう。全文はISIS 千夜千冊サイトへ
◎紀田順一郎氏(季刊『本とコンピュータ』1998年冬)
「中世ヨーロッパの情報文化」という副題から窺えるように、当時の写本や初期活字本がどのように情報の伝播に貢献したかを論じているが、興味深いのは、聖書その他の書物を暗記する必要から、中世の書物制作者たちは、当時の記憶術に則って図版やレイアウトを決定していたという指摘である。
現在の私たちは、西洋の古い本にある飾り文字やイラスト、あるいはレイアウト全体を単なる絵入り本の流れの中でしか見ようとしないが、これらは「平板なテキストに区切りをつけ、枠組みを補助する必要」から生まれた、記憶力を補助する工夫で、美術的な要請から生まれたものではなかった。いわば「視覚的な文法」である。
フランセス・イェイツに見るまでもなく、西洋には記憶術をきちんとシステム的に扱う伝統が脈々として存在し、この面では南方熊楠や吉田東伍のような個人の超能力だけに頼ってきた日本ないしは東洋と著しい対照を示している。なぜ記憶が重要かについては、12世紀の教師でサン・ビクトールのフーゴーの「学んだことを記憶に留めない限り、何かを本当に学んだ、あるいは英知を養ったということにはならない。教育の高揚は、教えられたことを記憶するという、ただその一点にある」ということばがすべてを物語っている。
◎池上俊一氏(『史學雑誌』1998年7月)
これまで思想史家も修辞学者もまともにはとり扱わなかった中世の記憶が、知識の中核をなすに止まらず、中世文化の属性であり、社会慣習であり、さらに道徳心の形成に役立つ教育的価値を内在させたものであったことが、本書によりはじめて明らかにされた。中世がなぜ千年以上もつづいたひとつの「時代」として理解することが可能なのか。それはたんに中世が古代と近代の中間にあるからだけではなく、人間の価値と行動の継続的源泉としての記憶が中世全体を覆っていたからであり、その記憶が現代の歴史家の直観に訴え掛けるからだろう。
記憶力を人間諸力のうちでもっとも偉大だと看做し、それゆえに記憶術に工夫に工夫を重ねた中世ヨーロッパのあり方は、記憶を自分たちの脳や身体からは放逐し、空虚な電子空間に委ねて喜んでいる現代の一種の病状への処方箋になるかもしれない。