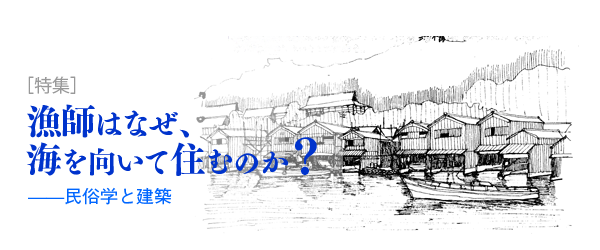
 |
2012年6月末に刊行した『漁師はなぜ、海を向いて住むのか?』が好評だ。著者地井昭夫さんは、早稲田大学建築学科、大学院修士課程・博士課程に学び、吉阪隆正に師事。地域計画家・建築家、さらには漁村研究者という肩書きを持つ。吉阪研究室時代から漁村の集落研究を手がけ、漁民の生活スタイルを活かした地域計画・復興計画にかかわり続け、2006年に亡くなった。 |
タイトルの「漁師はなぜ、海を向いて住むのか?」は、本文の中でも再三問い続けたテーマ。「海に近いほうが便利だから」とか「海を見て出漁を決めるから」といった理由を却下し、「海への信仰心」という結論を導き出した。漁港は極楽浄土/龍宮城へ行くための〈門構え〉なのだと。
荒唐無稽な考えに思われるかもしれない。しかし、次の文章を読んでほしい。
「集落(村落の意味における)、あるいはムラというものが、私達にとって、〈置き去られたもの〉 〈古いもの〉 〈何とか救ってあげなければいけないもの〉を意味するものになりつつあるのではないかと怖れている。それはまた、私達建築家が、この語の意味するところについてきびしい問を自らに課さないとすれば、ちょうど初期の人類学などが犯した、あのニューギニアあたりの原住民の道具を集めて来て、〈人類の故郷〉などと称した厚顔無恥な基本的な誤りを私達の同胞に対して、新たに犯すのではないかという怖れでもある。…むしろ私達にとって、古くてなんとかしなくてはならないものは都市ではなかったのか」(「1-2 丹後・伊根浦の研究・序」より)
率直な物言いから、地井さんの人柄がしのばれる。同じ論のあとがきにはこんな言葉にも出会える。
「多くの調査の中でいつも感じてきたことであるが、漁師たちはいつも明るく、勇敢であった。これは歴史の中でもはっきりとみることができる。こんなに明るい、力強い人々と、その生活が日本にあることについて、私達はあまりにも無知であったのではないだろうか」
フィールドワークをとおして常に漁村の人々に交じり、同じ目線で研究を進め、その後40年間もこの姿勢を貫き通した。東日本大震災の後、漁港の復興に力を尽くす人々をみるとき、この「海への信仰」が説得力を持って迫ってくる。
こうした民俗学的アプローチは「第1章 来訪神空間としての漁村」にまとめられた。2章以降は、漁村の家族論、自らが実践した草葺き家での農村生活、島と本土を連携させた防災論など、本書のテーマは多岐にわたり、それは地井さんの研究の幅広さを物語る。
本書からひろがる書籍を紹介したい。
【フィールドワーク】 | ||
 |
日本の民家今和次郎 早稲田大学建築学科出身の地井さんにとって、同学科で長らく教授を務めた今和次郎の影響は計り知れない。今和次郎-吉阪隆正-地井昭夫という系譜が自然と浮かび上がる。 今和次郎といえば考現学の提唱者。街を歩く人々の風俗を観察した考現学は、路上観察学の源流ともいえ、汐留ミュージアムなどでの「採集講義展」もたいそう話題になった。その今が考現学の前に柳田國男らの民家研究に参加し、その後はひとりで全国の民家をフィールドワークした成果が本書である。東京美学校卒業ならではの腕前で、数多くの民家のスケッチが収録されている。 冬は雪に閉ざされる津軽の農家の家、防風林を持つ九十九里浜の漁家、清水港の町家、薩摩揖宿(いぶすき)の農家などを描き留めていく。文章もまた味わい深く古さを感じさせない。 「雪消えどきには四月の陽にかがやいた林檎の樹の枝が、紫色の海のようにひかっていて岩木山という行儀のいい山がそれらの上に平野を越えて、真白に見えて、反対の方には八甲田の山脈が、もう冬もやんだぞという風に連なっている。大人たちは秋に春にこの野原で仕事をしているとき、北の国の子供たちはただ空想の国におかれているだけなのである」 90年後の民家を実地調査した『今和次郎「日本の民家」再訪』(瀝青会)が平凡社から刊行され、変わらぬ人気のほどがうかがえる。それにしても本家の『日本の民家』が品切れなのは残念。 |
|
 |
日本の村・海をひらいた人々宮本常一 『漁師』本文中で何度も「私淑している」と名前が挙がるのが民俗学者の宮本常一。今和次郎の30年後に生まれ、全国各地を歩き、人々の視点にたった独自の民俗学を打ち立てた。代表作『忘れられた日本人』をはじめ、数多くの著作があるが、ここでは漁村に関連して『日本の村・海をひらいた人々』をとりあげたい。 これは子ども向けに書かれた本で、前編「日本の村」は今和次郎の『日本の民家』のように地方の村々の家や暮らしのなりたちが描かれ、後編の「海をひらいた人々」には、福岡県鐘ガ崎の漁民が遠く能登半島の輪島や舳倉島(へくらじま)にも分村をつくった経緯などが、やさしく綴られている。その舳倉島は『漁師』の第1章で、〈舟住まいの陸上がり〉の実証例として紹介された地。本書を読んでから『漁師』を読むと、地井さんの興奮が伝わってくるはずだ。 「…私は膝のふるえをおさえることができなくなった。それはまさに宮本仮説の「生き証人」とも言うべき住居跡が、次々と発見されたからである」(『漁師はなぜ、海を向いて住むのか?』「1-1 住宅と集落はどこからきたのか?」より) |
|
【日本の風土】 |
||
 |
舟小屋 風土とかたちINAX BOOKLET 地井さんが漁村研究をはじめるきっかけは、京都丹後・伊根浦の舟小屋だったという。舟小屋、つまり舟を収蔵するための小屋は日本海側に多く残っている。この本には新潟は糸魚川市筒石から、能登半島、若狭湾、島根県隠岐までの13カ所の舟小屋がカラー写真で収められている。 これをみると舟小屋の形が地域によって異なることがよくわかる。伊根の舟小屋の多くは1階に舟置き場、2階を住居として見事に保存されているが、かえって例外なようだ。たいていは2階があっても漁具置き場だったり、舟を覆う屋根がある程度だったりといたって素朴な造り。 神崎宣武や中村茂樹、畦柳昭雄各氏のエッセイも写真を補強してくれ秀逸。ただしそのエッセイの傍らに「各地の舟小屋」がレイアウトされているのはちょっとわかりづらいが、デザイナー祖父江慎さんの大胆さゆえ、か。 |
|
 |
茶室とインテリア 暮らしの空間デザイン内田繁 タイトルに「茶室」とあるから茶室の本だと思っている人が多いようだが、もっと幅広い「日本的建築空間」について日本の風土や身体感覚からやさしく説く本。 日本人は家に入ると靴を脱いで床に座る、という私たちが普段なんの疑問を持たずに行っている行為から語り始める。床に座るだけならアジアでよく見られるが、履物を脱ぐという行為は日本と韓国だけ、通常はどの地域でも聖なる場へ入るための行為なのだから、家自体が聖なる場所という認識があるのだろうと。そして、西洋建築とは異なる日本のオリジナリティを紹介していく。 ハレの日には襖を出して日常空間を祭礼空間に一変させ、夏になれば障子を入れ替え風通しを演出し、ある日は庭に毛氈を一枚敷くだけで一つの建築空間にするなどなど。建築家アアルトが「引き戸」を取り入れたように、日本的暮らしの美点の数々を教えてくれる、まさしくCOOL JAPANな本。世界的にも賞賛されているのに、肝心の日本人が気づいていないなんて。 |
|
【土地から浮かび上がる】 |
||
 |
空間に恋して 象設計集団のいろはカルタ象設計集団=編著 地井さんと同じ吉阪隆正門下生が創設した象設計集団とは創立時にいっしょに仕事をしている。初期の代表作、名護市庁舎や安佐町農協町民センターは、地井さんと象設計集団の共作だ。 象設計集団の33年活動記録『空間に恋して』の中に、安佐町農協町民センターの写真が収められている。緑豊かな町にそびえる瓦屋根のドームに度肝を抜かれたものだ。『漁師』には設計をめぐる「エトスとしての農村空間」が収録され、その背景が解き明かされた。あれは〈地域の条件に即した破壊的、非科学的建築〉だったのだ。もう一つの共作、名護市庁舎も、沖縄の神と人が交信する聖なる場所「アサギ」を活かす点など、まさしく民俗学と建築の融合。 |
|
 |
月島物語ふたたび四方田犬彦 ここからは地井さんとは接点はないが、テーマがつながる本をとりあげたい。「土地」という言葉から想起したのが『月島物語ふたたび』。80年代、NYから帰国したばかりの著者が移り住んだ月島は、植木が繁茂する路地、もんじゃ焼の匂い漂う商店街。鍵も要らない長屋暮らしの描写をはさみつつ、きだみのる、大泉黒石、吉本隆明、黒澤映画の「酔いどれ天使」、水上生活者など、月島に来歴する文化人や市井の人々を調べあげ、土地の物語を浮かび上がらせた。漁村とはひと味違う、近代が生んだ水辺の物語。 最初の集英社版『月島物語』が92年刊行。99年の集英社文庫版では書き下ろしエッセイ「月島への旅の追憶」、そしてこの工作舎版では建築史家・陣内秀信さんとの対談およびエッセイ「月島二〇〇六」が収録されている。版を替えるたびに新たな文章が追加され、月島という土地の定点観測の記録にもなっている。これを読むと、バブル期のウォーターフロント開発が一段落した後は、超高層マンション、観光的なもんじゃ屋ブームへ移行したこともわかる。 |
|
【時の流れとともに】 |
||
 |
喪われたレーモンド建築 東京女子大学東寮・体育館東京女子大学レーモンド建築 東寮・体育館を活かす会=編著 『月島物語ふたたび』が都市の変貌の記録としたら、建築の変化も注目に値する。つまり老朽化した際、保存計画の道をとり後世に残すか、あるいは解体消滅させるかだ。今日、近代建築の多くがその岐路に立っている。ライトの弟子、アントニン・レーモンドによって造られた東京女子大学の校舎もその一つ。レーモンドがグランドデザインから手がけ、広いキャンパスに一体性をもって配置した校舎等9棟は、1938年に完成した、まさに貴重な歴史的建造物だ。しかしそのうちの東寮と体育館だけが、2006年突如整備・解体されることになった。それは保存を願う卒業生たちの闘いのはじまりでもあった。3年余りの活動の後、解体を防げなかった活動の全記録を残す。 |
|
 |
廃棄の文化誌 ゴミと資源のあいだケヴィン・リンチ=著 自然の循環、生命活動では、廃棄は不可欠なプロセスだ。『都市のイメージ』のケヴィン・リンチの遺作『廃棄の文化誌』は、建築の廃棄はもちろん、人口流出による都市の衰退、排泄、死、核廃棄物など、幅広い視点から廃棄を採り上げる。 廃棄すること=破壊することの喜びを挙げたと思うと、リサイクルの意外な諸例が紹介される。臓器移植も身体のリサイクルであり、ゴミの山から有益な物を探し出す人々もいる、それが古代ローマのゴミとなれば考古学者が大喜び。ゴミも悪いものではあるまい。 一方、時間にもあてはめれば、時間を捨てないように「効率」に注意が向く。しかし効率のよい鉱山は膨大な廃棄物の山を生み出し、汚水も流れ出るものだ。そう考えると効率優先は別の面では不健康で不快なものかもしれない、と。 リンチは廃棄を一方的な悪者に仕立てず、絶えず両面を見据える。廃棄/衰退がいずれ避けて通れないものならば「上手に廃棄する」あるいは再利用することを説く。今こそ読まれるべき本だ。 |
|

