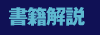地球外生命論争1750-1900 まえがき
◎
天文学者は、明日か、一年後かあるいは一世紀後にも、今までに科学者が追求してきた最も重要な発見のひとつ、地球外文明を発見するかもしれない。そのような文明と接触すれば、おそらく最も急を要する科学的、技術的問題も解決され、さらに驚くべき成果がもたらされるだろう。また、今までしばしば言われてきたように、地球外生命の決定的な証拠が発見されれば、それは哲学・宗教・社会思想などに対して広範な影響を及ぼすだろう。
◎
本書には、上述の二つの発見のどちらよりも控えめなひとつの発見が含まれている。それはほとんど各頁に現われているが、ひとつの文章で要約することができる。すなわち、地球外生命の問題は今世紀に始まったのではなく、ほとんど歴史の初めから議論されてきたということである。ギリシア文明が最盛期を迎えた紀元前五世紀から一九一七年までの間に、一四〇以上の著作と、何千もの論文、評論、そしてその他の文書で、居住者の存在する世界が宇宙に別にあるかどうかが論じられてきた。さらに本書の中で文献によって立証したように、一七〇〇年頃以来、教育をうけた人の大多数は地球外生命の仮説を受け入れ、多くの場合それに関連した自らの哲学的・宗教的立場を形成してきた。別の言い方をすれば、たとえUFOが空に浮かんでいなくても、地球外生命を信じる気持ちは、人間の意識の中に何百年もの間浮かんでいたのである。月や火星が巨大なレンガのように不毛であるとしても、月人や火星人はずっと以前からわれわれの文化に入り込み、われわれの思想に影響を与え、そして今や映画や文学作品の中でますます大きな役割を占めているのである。ギリシアの神々が存在しないと同じく、われわれの考える地球外生命も存在しないかもしれないが、それらの影響は同様に否定できない。被害妄想が現実の生活を壊したり、無神論者が信仰の影響を認めたりするように、われわれは地球外生命の侵入がずっと前から始まっていたと考えるべきである。要するに本書は、たとえ地球外生命が存在しなくても、その地球上への影響は計り知れないものであったという信念に基づいて書かれているのである。
◎
本書の焦点となっているのは、宇宙の他の天体に生命が存在するかどうかという問題に関して、ひとつの惑星で一七五〇年から一九〇〇年頃までに展開された論争である。しかし本書は、単なる過去の無味乾燥な記述以上のものを構想しているし、この長い論争の現状にささやかな貢献ができることを期待してもいる。ピエール・デュエムが同様の文脈で述べているように、一つの理論の歴史を述べることは、それを批評することでもあるからである。従って、本書で論じる人々が支持した考え方を正確に記述するよう努めるとともに、ためらわずに彼らの立場を検討し、それらに評価を下した。そしてさらにより大きなパターンや原理を追求した。その中には、この論争の中で現在問題となっている事柄に示唆を与えるものがあるように思われる。
◎
一八世紀の半ばから二〇世紀の初頭までの期間に焦点をしぼる決心をしたのは、多くの要因を考慮したからである。古代から一八世紀前半までの展開については、最近スティーヴン・J・ディックが『世界の複数性──デモクリトスからカントにいたる地球外生命論争の起源』(Plurality of Worlds: The Origins of the Extraterrestrial Life Debate from Democritus to Kant 以下『世界の複数性』)の中で見事に論じた。この本のおかげで、この期間の資料については簡潔に済ますことが可能となり、本書では第1章だけをその期間に充てた。今回の研究を二〇世紀初頭までに限定したのは、その頃までに現れた資料が膨大な量であることと、それらの資料の大多数(その多くは非常に珍しいもの)から直接得た知識に基づいてこの研究を行おうとしたからである。これらの資料が一般的にカバーしている時代は一九〇〇年までであるが、火星の運河論争に関しては、それが全盛を迎えた一九一〇年頃にまで及んでいる。
◎
頭を痛めた問題は、どの資料を検討すべきかという選択であった。SF作品は長くそして優れた歴史をもつものであるが、このジャンルのものは基本的にすべて除外した。この分野の文献が膨大であること、さらに、実際に人間が信じている事ではなくて、想像しうる事について述べる傾向があるという理由で、このように決断せざるをえなかったのである。ただし話を進める上で触れる必要があった二、三の場合は例外である。しかし、本書で扱った話題がSF史の研究家によって光を当てられたこともたびたびあり、本書が彼らにとっても価値あるものとなることを期待する。
この研究で特に対象としてきたのは、天文学関係の文献であり、初めのうちはそれだけに集中した。しかし、科学的な仮説よりも形而上学的な前提あるいは宗教的な原理により近いと思われる観念の研究に際しては、科学的アプローチ、哲学的アプローチ、宗教的アプローチなどと明確に区分しない方が望ましく、またそれが可能でもあるということがすぐに明らかになった。事実、世界の複数性の概念に関しては、天文学・文学・哲学・宗教のそれぞれの立場の議論を隔てる明確な境界がないということが、まさに本書のテーマのひとつなのである。
◎
地理的には、ヨーロッパと北アメリカの国々に集中することになった。これらの国々の間には相互に影響があったが、東洋、アフリカ、南アメリカの考え方とは影響関係が乏しかったということで、著者のこの選択を正当化することはできないであろう。むしろ、著者が東洋やアフリカの諸言語の知識に乏しいために、思想を原典にまで遡って探究しようとした時に、こうした地域を除外せざるをえなかったのである。
本書を執筆するにあたって想定した読者は、地球外生命に関心をもつすべての人々であり、特に、われわれの最も興味をそそる探究のひとつに、われわれ地球人がどう対応してきたかにまで関心をひろげる人々である。一般の読者はおびただしい出典を無視されてもよい。というのは本書は研究者、特に科学思想史の分野の同僚による、綿密な調査に耐え、それに報いることができることを期して書かれたからである。宗教史家および神学史家もおそらく予想以上の参考資料をここに見いだすことを期待したい。また、文学や哲学の発展に関心を持つ人々も、この研究が彼らに直接関わる問題に光を当ててくれると思われる場合があるかもしれない。こうしたさまざまなな分野に言及しても、本書に次々と出てくるおびただしい数の個人をカヴァーするにはまだ十分ではないであろう。しかし論争に加わったアラゴとアリストテレス(A)、バルザックとベートーヴェン(B)、カヴールとチャーマズ(C)、ダーウィンとドストエフスキー(D)、エマスンとエンゲルス(E)、フラマリオンとフランクリン(F)、ガリレオとグランヴィル(G)、ヘーゲルとハーシェル(H)らの名前を挙げれば、別の世界を考えるという関心はほとんど学問そのものと同じほど広いものであったっことが分かるであろう。
◎
読者は、本書が上記の資料を検討しながら英語で書かれた最初の詳細な学問的研究だと思われるかもしれない。しかし既存の多くの著者の出版物から得るところが極めて多かったのである。その中でも、この研究が最も直接的に恩恵を受けた十名は、R・V・チェインバーリン、S・J・ディック、S・L・エンダール、C・フラマリオン、K・S・グトケ、W・G・ホイト、S・L・ジャキ、A・O・ラヴジョイ、G・マコリ、そしてM・H・ニコルスンである。 彼らの著作は本文の至る所で繰り返し言及されているが、それでも彼らの学識にいかに負うているかを十分に表しているとは言えないだろう。読者はまた、本書が大部であるとはいえ、その構想は決して完成してはいないという著者の思いに気づくかもしれない。確かに地球外生命に関する結論の出ない論争は将来へと続いていくだろうし、過去の論争に関する研究も続いていくことが期待される。