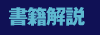親鸞への接近[詳細]
親鸞がきみを選んだ。
世俗のしがらみを拒絶し、学問に打ち込んだ道元。
自力の修行を拒み、非僧非俗で平然と妻帯をした親鸞。
学生時代に著者は道元には惹かれたが、親鸞を前にためらいを感じた。
親鸞はこうして封印された──。
ところが後年、戦地と占領地で、人間の巨大な悪を前にしたとき、
著者の前に再び親鸞が立ち現われてきた。
自分の意志で手にとったのではなく、親鸞が接近してきたのだ──。
■目次 |
▲ |
親鸞とわたし
『歎異抄』について
『教行信証』論
1 ひそかにおもんみれば
2 海の隠喩、光
3 ガンジスの砂の数ほどの引用
4 際限のない羅列
5 水平移動
6 誓願
7 アジャセ
8 テクストの過剰
『歎異抄』のスタイル
1 来歴
2 編纂された対話
3 封印
4 さまざまな聞き書き
5 口伝と註釈
6 悪人正機
7 対話の構造
8 業縁とモンタージュ
9 正統と異端
10 辺地の悲嘆
和讃と今様
仏教用語翻訳の難しさ
礼如さんの思い出
赦すということ
三木清 終末の近傍で
1 プロローグ
2 三木清と親鸞
3 戦時下の位置
4 懺悔と機
5 末法とは何か
6 無戒
7 自督
三國連太郎 差別への眼差し
1 オルレアン
2 俳優としての三國連太郎
3 小説『白い道』
4 差別への眼差し 三國は親鸞に何を学んだか
5 『親鸞 白い道』
6 フィルムの分析
7 『朽ちた手押し車』
吉本隆明と〈解体〉の意志
1 資質の問題
2 晩年
3 愚の体現
4 無場所としての浄土
5 実体なき衆生
6 「はからい」とは何か
7 二人の戦中派
あとがき
■関連情報 |
▲ |
●2018.9.16 毎日新聞朝刊三八広告
お彼岸仏教企画として四方田犬彦著『親鸞への接近』の三八広告を出しました。西日本は9月18日(火)掲載。

●2018.9.11-10.1 三省堂書店神保町本店フェア
2F文芸フェア台にて「蔵出し!四方田犬彦の本棚」開催>>>
●2018.8.24-9.15 東京堂書店神保町店 四方田犬彦さんトーク&サイン会開催
「人はなぜ生涯のある時点で親鸞と出逢うのか」>>> 報告>>>
同店3Fにはブックフェア「四方田犬彦を読み尽くせ!!」8.17-9.15>>>

■書評 |
▲ |
●2018.11 同朋(真宗大谷派宗務所発行)
連載「親鸞万華鏡」に著者・四方田犬彦さんインタビュー
世界の現実のただ中で
…近代以降の日本の知識人の中に、人生の最後にあたって親鸞についての本を遺す人が多いのはなぜだろう、ということでした。おそらくその人たちは、日本が西洋の思想や文化を取り入れた後で、何か取り落とした巨大な存在としての親鸞に気づいたのでしょう。このことは、近代日本の思想や文化のあり方を考える上で避けて通ることのできない大きな問題だと考えています。
●2018.10.7 北日本新聞など地方紙に 藤沢周氏評
緻密さに「他力」の妙味
…「蔓や地上根が複雑に絡み合う、南国の密林に迷い込」むような大部の「教行信証」、親鸞の言葉を編んだ弟子・唯円の「独自のドキュメンタリー作品」でもある「歎異抄」。この2著を緻密に丁寧に読み込み、ほどいていく著者の筆致にまずは圧倒され、ため息が震え漏れる。
親鸞と著者の同行の足取りがぴったりと合えば、衆生を想う魂の悲痛なほどの叫びが聞こえることもあり、また乱れたりするときには、逆に仏の光の塵が喜び、舞うかのようである。四方田犬彦という著者が「自力」で親鸞を選び、書いた、というよりも、親鸞が著者を選び、書かせたという「他力」の妙味を覚えるのだ。…

10/13 北国新聞、福島民報
10/14 新潟日報、日本海新聞、東奥日報、下野新聞、山陰中央新報、山陽新聞、神戸新聞、愛媛新聞、大分合同新聞、宮崎日日新聞
10/21 京都新聞、福井新聞、四国新聞
11/4 岐阜新聞、徳島新聞、南日本新聞 計23紙に掲載されました。
●2018.10.12 週刊読書人 島田裕巳氏評
42年前の思い出
「新約聖書」をモデルに 『教行信証』から『歎異抄』へ
それは、今から42年ほど前のことだ。
私は東京大学文学部宗教学科の学生で、卒業論文の口頭試問に臨もうとしていた。控え室にあてられた研究室で順番を待っていると、そこに、私より順番が一つ前の四方田犬彦が戻ってきた。当時彼は小林剛己を名乗っていた。
…
親鸞に接近するための時間が自分のなかで少しずつ熟していったことにふれ、最後には親鸞の主著についてとても印象的なフレーズが使われている。「わたしが『教行信証』を手に取ったのではなく、『教行信証』が私を手に取ったのだ。
これはもしかして、著者自身の回心体験から発せられたことばではないのか。私はそう感じた。…
[全文は週刊読書人サイトへ]
●2018.10.7 読売新聞 苅部直氏評
絶対へのまなざし
「親鸞がきみに接近してきたのだ」。この本の冒頭近くにある言葉が、分厚い書物全体にわたって、底流として流れている。「きみ」は表題どおり「親鸞への接近」を試みつつある著者自身。しかし、親鸞の側が「きみ」を選んだと語り、世界で生じるすべての出来事が窮極において阿弥陀如来の「はからい」に由来すると説くのは、いったい誰の声なのか。…
[全文は読売新聞サイトへ]

●2018.10.6/10.13 図書新聞 稲賀繁美氏(連載「思考の隅景」)
ひとはいつ・いかにして親鸞に呼ばれるのか
日本信仰思想史における宿命の周期律
…本書は懼るべき書物である。だが「おそるべき」などという形容は、その達成を裏切る。達成といったが、努力の末に知的な頂きを極めるというのではない。反対に、登頂の野望が孕む危うさを、登頂に勝る努力によって踏破している。だが「あとがき」で著者は「とりあえずここまでは考えてみた」が「その先は遥かに遠いだろう」との感慨に耽る。「大きな誤解」なきやを恐れ、己の「非力」を表明する著者だが、それは自己韜晦でも自惚れでもない。「他力本願」が成就されるとは何を意味するかを理詰めで追った結果だからである。…[全文は図書新聞サイトへ]
●2018.9.7 林哲夫氏(ブログ「daily-sumus2」より)
「五百頁を超える厚冊。一目ビビったが、読みはじめてみると、理路整然たる筆致によって知的興味を刺激されながらスイスイと読み終った。
これほどの圧巻について短評で云々するのは不可能。しかしそこを敢えて一言で、例えばオビの惹句をひねり出すごとく、軽々に表現すれば、「文学として親鸞のテクストを読む」、これに尽きる。宗教でもなく歴史でもなく文学である。…」
続きは「daily-sumus2」9/7へ。9/9には「教行信証」について。