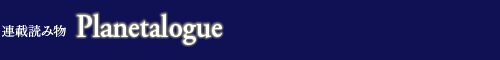第4回 スーパーエディターとの交流
『新潮』10月号に一挙掲載された筒井康隆の最新作『モナドの領域』が話題をよび、同誌はたちまち増刷されたとの由。人間に憑依したGODがライプニッツ君の哲学を注解する意表をつく展開、さながら神自身による『弁神論』を読むようで倦む暇もなく読了してしまう逸品です。末尾の謝辞には、季刊『哲学』創刊号でライプニッツを特集し、その後もたびたびライプニッツを紹介した編集者・故中野幹隆氏と同誌の常連だった山内志朗氏の名のほか、参考資料として同誌8号掲載の岡部英男訳「偶然的真理と必然的真理」などが記されています。
ライプニッツが生前に公刊した唯一の大著となった『弁神論』(第I期6・7巻)を著したのも、『学芸共和国通信』の編集者ピエール・ベールとの交流がきっかけでした。
南フランスの改革派(カルヴァン派)の牧師を父にもつベールは、イエズス会の学院に学んだおりにカトリックに改宗したものの改革派への復帰を決意してスイスに逃亡。ジュネーヴ大学でデカルト哲学を学んだのちにプロテスタント系のセダンの大学に哲学教授として招かれフランスに戻りますが、故国のプロテスタントに対する弾圧は厳しくなる一方で大学も閉鎖に追い込まれ、オランダに移住。ロッテルダムの高等教育機関で哲学と歴史を講じますが、12年後には諸般の事情で罷免……というように波瀾の青・壮年期を送りました。
ライプニッツとの縁は、ベールがロッテルダムで創刊した『学芸共和国通信』1686年9月号に、ライプニッツが『ライプツィヒ学報』に発表したラテン語論文『自然法則に関するデカルトおよび他の学者たちの顕著な誤謬についての簡潔な証明』(第I期第3巻)の仏訳と、それを批判するデカルト派のカトラン神父の論文を併載したことにはじまります。
パリ王立諸学アカデミーの『学術雑誌』、ロンドン王立協会の『哲学紀要』が1665年に相次いで創刊され、67年にはローマの『学芸雑誌』、82年には『ライプツィヒ学報』と続いて国境をこえた学者のネットワークが形成され、メディアを通した論争・学術交流が盛んになっていました。84年に創刊されたベールの『学芸共和国通信』は、学者だけでなく世俗の人も読者対象とされ、前半部には論文やその抄録、著者の略歴、作品や論争の寸評、後半部には寸評つきの新刊紹介を掲載。最前線の学術動向への目配りと的確な編集センス、明快な論評で、フランスでは禁書とされたにもかかわらずヨーロッパ中で支持されたようです。
ハノーファーのライプニッツも同誌のカトラン神父の反論を読み、公開を前提にしたさらなる反論の手紙をしたため、添え状とともに送ったことでベールとの往復書簡(『哲学書簡』第1部6)がはじまりました。
デカルト派のマルブランシュやカトランとライプニッツの「力」の保存をめぐる論争はこうして『学芸共和国通信』を舞台に続けられますが、ライプニッツの第1信を受け取ってまもなくベールは過労で倒れ、同誌の編集から離れざるをえませんでした。
そうこうするうちに教職も失ったベールは、むしろ幸いとばかり執筆活動に専心。かねてより「辞典類やその他の図書に散在する無数の誤りを訂正する批評辞典の腹案」と予告していた大著に猛然とりかかり、『歴史批評辞典』を刊行します。
18世紀の啓蒙思想家に多大な影響をあたえた『歴史批評辞典』は、たんに項目を並べて説明した辞典ではなく、項目の解説に加えて脚注を付し、さらに傍注がつくといった重層構造。ライプニッツについては主項目ではなく、15-16世紀の神学者「ロラリウス」の解説記事に名前を出し、その長大な脚注でライプニッツが『実体の本性と実体相互の交渉ならびに心身の結合についての新たな説』(第I期第8巻)で展開した予定調和説を批判したのでした。
これを読んだライプニッツは、しばらく途絶えていたベールとの交信を再開。ベールからの手紙にはベストセラーとなった『歴史批評辞典』の第2版の増補に多忙をきわめているようすがうかがえ、コピー機もコンピュータもない時代に大著をものしたベールの底知れぬエネルギーに驚嘆するばかりです。
ベールの批判に応えることはライプニッツ終生の原動力となった感があり、『モナドロジー』(第I期9巻)でも言及していますし、ゾフィー、ゾフィー・シャルロッテ母娘との会話でもたびたび話題となったようです。薔薇十字運動のシンボルでもあったエリザベスとフリードリヒ5世の血をひくこの二人の貴婦人は、1700年のオランダ旅行のさい、ロッテルダムでは都合のつかなかったベールをハーグまで呼び出して会見したと伝えられています。
『弁神論』(1710)は、早逝したゾフィー・シャルロッテ追想の書であり、ベールへの反論の集大成の書でした。同書の序文で、ライプニッツはベールのことを「弁舌も洞察力もともに優れ、博識を余すところなく発揮」し、「事物の根本に関わること以外では私よりも優れている」と称えています。同書は一歳下ながら先に逝ったベール追想の書でもありました (十川治江)。