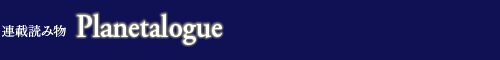第3回 パリのドイツ人
ライプニッツがパリに滞在した1672年から76年のあいだ、フランスは太陽王ルイ14世の治世のもとにオランダ侵略戦争を続けながらもコルベールを中心に文化政策を積極的に推進していました。1666年創立の諸学アカデミーは、土星の環を自作の望遠鏡で発見したオランダ人クリスティアン・ホイヘンスにも計画案を求めて組織化されており、ホイヘンスは初代会員として活躍中でした。
ライプニッツが初めてホイヘンスを訪ねたのは1672年の秋。数学的直観と機械学的センスを併せもつ二人ならさぞ意気投合したことでしょう。ライプニッツに必読書や課題を示して当時の数学の世界水準へと導いたのは、ホイヘンスでした。
ロンドンの王立協会につづいて、パリ諸学アカデミーでもライプニッツは計算機やクロノメーターを披露し(1675)、コルベールから計算機3台を受注したとのこと。モノができて納品できれば万々歳なのですが、そこは未完の天才……。
数学に加えてライプニッツがパリ時代に磨いたのは、ラテン語に代わって当時の国際語になりつつあったフランス語。パリ滞在も半ばをすぎた時期(1674/75)にマルブランシュに出会えたのは、ライプニッツにとって思想的錬磨のうえでもフランス語修練のうえでも幸運なことでした。
『マルブランシュ全集』全20巻を編集したアンドレ・ロビネ先生は、第I期第5巻『人間知性新論』下の「発見術への栞」に寄せた「『人間知性新論』の現代性」と題する一文で、下記のように晩年のライプニッツのフランス語を賞揚しました。
『人間知性新論』は非の打ち所のないフランス語で書かれており、17世紀の偉大なフランス語に列する。ライプニッツはそれをパリで身につけ、迅速に活用し、科学的哲学的な文通を行なった。『人間知性新論』のテクストはマルブランシュの諸作品とともに古典フランス語の優れた見本であると日本の哲学研究者たちに申し上げたい。
第1巻『哲学書簡』に収録した書簡のうち、冒頭よりトマジウス、ホッブズ、スピノザ、アルノー宛の書簡はすべてラテン語で書かれたものですが、マルブランシュ以降、ベール、ゾフィー、ゾフィー・シャルロッテ、マサム夫人宛の書簡はすべてフランス語で書かれています。
『哲学書簡』に収録したマルブランシュ宛の第1信(1676 前半)は、「帰宅して、お互いに議論したことを省察しました」ではじまるとおり、会見当日の興奮さめやらぬ調子で書かれています。会話では十分に伝えられなかった見解を文章で整理して名文家マルブランシュに見てもらう、こんな贅沢なフランス語演習はありません。
これに対するマルブランシュの返信は、「会話に終始する議論よりも筆になる議論のほうが、はるかに多くの時間がかかり」めんどうというもの。
ライプニッツは次信で、「理解力や自分の考えを述べる力をもつ人々は、筆になる議論よりも会話の中により多くの快を見出す」でしょうが、「私のように鈍重な者には、そうした会話に付いていくことができないのです」と言い訳をしています。
監修者のお一人、佐々木能章先生は、下村寅太郎・山本信両先生のもとで第I期著作集の第8・9巻の収録論文を検討するさい、このやりとりを読んで、二人の哲学者本来の性向とは逆になっているようで興味深く感じられたとのこと。
さすがのライプニッツも、修得中のフランス語で当意即妙の議論をするのは難しかったようです。以後、マルブランシュをはじめ、ベールやアルノーとの往復書簡やサロンの貴婦人たちとの会話や書簡でさらにフランス語を磨いたライプニッツの若き日の姿がここにも示されています。
アウグスティヌス(信仰)とデカルト(理性)の統合をめざしたマルブランシュは、ライプニッツの動的力(活力)の考え方にも耳を傾けて自著に反映させるほど柔軟な発想の持主でした。いっぽうマルブランシュの著作がいかにライプニッツの著作に影響を与えたかについては、清水高志先生の解説を参照ください(十川治江)。