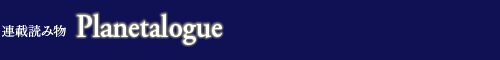第11回 ゾフィーの恩恵
ライプニッツは数学・自然学・哲学上の成果を後代に残すだけでなく、世界をじっさいに変えて同時代の人びとに実りをもたらすため、終生宮廷人として活動する道を選びました。理論と実践が統合されてこそ、普遍学は成立するからです。宮仕えの日々は不本意なことも多かったでしょうが、イングランド王ジェームズ1世の孫娘ゾフィーという庇護者にして触発者に出会えたことは、ライプニッツの人生をいちだんと豊かなものにしました。
ゾフィーの兄や姉は逸材ぞろい。長姉エリザベトについてはすでに述べたとおりです(第5回)。次姉ルイーゼ・ホランディーネは、カラヴァッジョの画風をオランダで広めたG・ファン・ホントホルストに師事した画家でもありました。現在国立西洋美術館で開催中のカラヴァッジョ展では、ホントホルストの「キリストの降誕」も披露されています。残念ながらルイーゼの作品は来ていませんが、彼女が描いた14歳頃のゾフィーの肖像画はWebで見ることができます。

ルイーゼ・ホランディーネによるインド人に扮した妹ゾフィーの肖像(1644年頃)
ルイーゼは弟エデュアルトの介添えでカトリックに改宗し、フランスのシトー会系のモービュイッソン修道院長となりました。彼女とその秘書ブリノン夫人が仲介役となり、ライプニッツとモーの司教ボシュエの新旧の教会再合同をめぐる往復書簡が交わされます(『法学・神学・歴史学』第2部収載)。ルイーゼは修道院に入っても、画業をつづけたと伝えられています。
ゾフィーの兄カール・ルートヴィヒは30年戦争を終結させたウェストファリア条約によりプファルツ選帝侯となり、ハイデルベルクの復興と学芸振興に尽力します。スピノザを招聘しようとして実現しませんでしたが、法学者プーフェンドルフをハイデルベルク大学の教授に引き立てています。
カールの長女エリザベト・シャルロッテは幼くして両親が離婚したこともあり、7歳で新婚間もない叔母のゾフィーに預けられました。4年にわたる多感な時期をゾフィーの影響を受けながら育ち、生涯ゾフィーを母のように慕っていました。19歳でルイ14世の弟、オルレアン公フィリップと結婚します。ライプニッツに会う機会はありませんでしたが、ひんぱんに手紙をやりとりしたゾフィーから送られてくるライプニッツの論考を読むのを楽しみにしており、直接ライプニッツとも書簡を交わしています。オルレアン公フィリップに仕えたニコラ・レモンに捧げた珠玉の小品が、『モナドロジー』と呼ばれるようになりました。
ゾフィーは運にも恵まれていました。彼女がエルンスト・アウグストに嫁いでエリザベト・シャルロッテを預かり、さらに実子6男1女を得たときまで、夫はオスナブリュック司教の地位のみで公位を継承する可能性はほとんどありませんでした。ところが兄ヨハン・フリードリヒの急逝により、エルンスト・アウグストがハノーファー公となってライプニッツの主君となり、さらにはライプニッツが序文として地球史『プロトガイア』から書き起こしたブラウンシュヴァイク=リューネブルク家史編纂の効果もあり、選帝侯となりました。
ゾフィーの一人娘ゾフィー・シャルロッテも才知に恵まれ、ライプニッツと古今の文学や哲学をめぐって書簡を交わすようになります(『哲学書簡』第2部2)。夫となったブランデンブルク選帝侯の嫡男フリードリヒは、ブランデンブルク選帝侯・プロイセン公となり、妻の進言により1700年にベルリン諸学協会を設立。ライプニッツを初代会長として招きました。ライプニッツの生涯のハイライトです。さらにフリードリヒはプロイセン王になり、近代国家としての礎を築き、孫のフリードリヒ大王の治世を準備しました。ゾフィー・シャルロッテのために夏の離宮として建設されたシャルロッテンブルク宮殿の庭園では、ゾフィーとゾフィー・シャルロッテ母娘とライプニッツが散策しながら語らい合って至福の時を過ごすこともありましたが、ゾフィー・シャルロッテは1705年2月1日、36歳で急逝してしまいます。
ゾフィーはまた、娘の夫フリードリヒが後見人となっていたブランデンブルク=アンスバッハ辺境伯ヨハン・フリードリヒの娘カロリーネをベルリンの宮廷で見出し、孫のゲオルク・アウグスト(後のジョージ2世)の妻に迎えました。
1714年6月8日、ゾフィーはカロリーネとともにヘレンハウゼンの庭園散策中に急逝します。ライプニッツはウィーンでアカデミー建設のために活動中で、ゾフィーからたびたびハノーファーに戻るように督促をうけていながら、戻れないまま受けた悲報でした。同年8月にはイングランドのアン女王が逝去し、ステュアート朝の血をひくゾフィーの長子ゲオルク・ルートヴィヒがイングランド王ジョージ1世となり、ゾフィーは現在にいたる英国王室の祖となりました。
カロリーネは皇太子妃キャロラインとしてイングランドに渡り、ニュートンとライプニッツの仲をとりもつようになります。
イングランドへの随行かなわず、ハノーファーに残されたライプニッツの晩年は寂しいものになりますが、執筆意欲は衰えず、キャロラインの仲介でニュートンの代理人サミュエル・クラークと往復書簡(9『後期哲学』)を交わします (十川治江)。