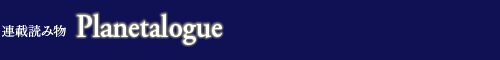第37回 下村寅太郎先生追想
第I期『ライプニッツ著作集』の監修を下村寅太郎先生にお願いしようと思ったのは、著書の『ライプニッツ』(弘文堂 1938; みすず書房 1983)で鮮やかに表出されたライプニッツ像と情動を喚起してやまない哀調をおびた文体に魅了されたからでした。『下村寅太郎著作集』全13巻(みすず書房 1988 – 99)を繙けば、今なお他所では得難い境地にひたることができますが、以下に著作集には収録されていないライプニッツに関わる3編を紹介して先生を偲びたいと思います。
◎若い日の私──「未完成」に協力したかった 下村寅太郎 (『毎日新聞』1990.7.26)
九十歳になったら、蔵書を手放してもよい、と約束したのであったが、最近その歳が目前に迫ってきていることに気付き、いささかならず驚きを感じた。どんなにやせ我慢を張っても、九十歳が限界であろうと、水増しの気分で約束したのだが、今も、毎日午前二、三時までは机前に座るに耐える日常であるから、いささか早すぎたと感じる。しかし、自分の生命の延長も自分だけではないから、単に自分だけの速断にすぎなかったのではないだろう。しかし時間の経過の迅速に改めて驚いたことは事実である。時間は必ずしも時計と同じように等速に進行するものではなく、遊戯中の一時間は、授業中の一時間よりも速いことは、小学校いらいの経験である。時間の流れが急速だったことは、退屈してはいなかったことであるから、よしとせねばならぬ。
いずれにせよ蔵書を手放す約束の日が迫ってることゆえ、整理に着手せねばならぬと、書架の前に立つが、ながく会わない旧友に出会ったり、苦労をともにした人に会う懐かしさに似た感じがするのはよいのだが、同時に、必読の書物でありながら未読であったり、忘却していた書物の意外に多いことに当面して、狼狽したり当惑したりする。これは転じて、自分の志したものが、力量不相応であったことによるので、遅滞は必ずしも怠慢によるのではないと自己弁護をするのだが、弁護であることには変わりはない。それとは別に、自分のとくに関心をもってきた思想家には著作の未完成の人が多いことに改めて気付く。ライプニッツやレオナルド・ダ・ヴィンチはみな未完成を特色とする人である。必ずしも意識して選んだのではなかったが、その動機の一つには、著作の未完成の性格の人であったことによるように思える。完成された著作の研究は、「復習」にほかならず、未完成の著作の研究は積極的にそれの完成に協力するのだという気分があったように感じる。若気のいたりに相違なく、稚気に満ちたものであるが、この「苦行」をあえてすることに悦びがあったことは確かである。他人を批判することよりも、創作に参与することに悦びをもつことであった。その成否に悔いなしとする青年の青年らしい情熱であったろう。少なくとも空想や着想の自由の悦びが予想された。そのため雑多な書物の雑読、乱読の傾向をもたらしたことも告白せねばならぬ。蔵書の雑多な堆積もその所産である。しかしこの蔵書には若干の脈絡はあるのだが、それは自分だけにしかわからない「秘密」であろう。ヒントは名著に限らない。創造は混沌からの創造である、は自己の弁でもあった。それ自身としては苦業ではあったが、自ら求めてする苦業のゆえに悦びがあった。改めて完成とは何であるかが考えられた。
レオナルドが絵画制作に集中せず、放恣な関心のために、天才を空費したと非難されるが、それは彼を狭い絵画史の枠の中に封じこめて、彼の独自性において理解しない偏見にすぎない。すべての人を「専門家」としてしか理解しない現代の短見でしかない。
歴史は、現実的にはいかなる場合にも常にあらゆる可能性をはらむものであって、それぞれの時代の常識で一律化すべきではない。現在の常識は現在の常識にすぎない。常識は常に浮動し一時的なものにすぎない。戦前の常識は、数十年以前のものなのに、すでに現代の常識ではない。我々は常識に依存しすぎる。ギリシャ人は全身像しか造らなかった。今日では、身体の一断片ですら「トルソ」として完成作品と見なしている。
◎『みすず』1991年読書アンケート 下村寅太郎(1992.1)
1『ライプニッツ著作集』(工作舎)
古代から現代に及ぶ西洋哲学の主な古典書はプラトンからハイデッガーにいたるまで略々邦訳されたが、近世哲学の劈頭を飾るデカルト、スピノーザ、ライプニッツの中、前二者は夙に全集に近いものが出現したが、その最大のものというべきライプニッツのみは、五十年前に河野與一氏の名訳二巻が出たのみで、その後一、二の小冊が出たのみである。河野氏訳は形而上学関係のものに止まる。ライプニッツ自身による単行本は、啓蒙的な二書(『人間悟性〔知性〕新論』と『弁神論』)のみで、今日彼の哲学上の主著とされている『単子論』は彼の弟子のために書かれた僅かに数十頁の小冊であり、標題すらなく、ずっと後にE・エルトマンの編集した著作集に初めて刊行され、「単子論」の名称も彼による。文字通り万学にわたる無双の博識の哲学者としては奇妙に見えるが、彼の時代は西洋の最初の世界大戦であった三十年戦争直後で、ドイツの全土が焼土に化し、独手その再建を志した者である。彼の学問的な努力が全学問にわたることも、学問的競争者も殆どすべて外国の学者であり、その著作も彼等宛の往復書簡や少数の学術雑誌に寄せたもののみであることもこれによる。これらのことがライプニッツ研究を困難にしている。完全な全集は未だなく──第一次大戦後ベルリン・アカデミーによって計画されたが八十巻予定のものが未だ十数巻しか出版されず、それの完成にはなお百年を要すると関係者は公表している。ライプニッツの全業績にわたる叙述は極く少く、今世紀に出たものは僅かに数冊にすぎない。わが国のライプニッツ研究や翻訳の乏しいのはかかる事情に負う。工作舎の著作集十巻は固より小規模のものであるが、出来る限り全貌を窺知し文字通り窺知(・・)の程度にすぎないが、論理学、数学、自然学、認識論、形而上学、宗教哲学等々に及び、わが国では最初の企画のものである。ライプニッツの著作はラテン語フランス語を主とし、ドイツ語は少しであるから、一ヶ国語で読み得るのは日本人のみであると、「全集」の編者の一人ハイネカンプ氏は讃辞を寄せている。殆ど初訳のものであるが、殊に最近刊のものには地質学、普遍学からシナ学まで及ぶものを含む。日本のライプニッツ研究もこの域に達したことは慶賀に堪えない。訳者並びに出版者の情熱に敬意を表したい。筆者自身その編者の一人で、自讃の譏りを甘受して敢てライプニッチアンとして研究者のためにビラ撒きの役を恥じない。
西欧の新しいライプニッツ研究書には「未刊行資料による」と標記したものが多いが、我々には現実的には未だ困難である。しかし既刊のものの中に未開拓未発見の珠玉が埋蔵されているのであって乏しきを憂う必要はない。周知のごとくライプニッツの学識は殆ど全学問に及び、各々の領域において独創的な着想の開発を待つもの多く、例えば、二十世紀の数学を風靡したトポロジーや現代の計算機の基礎となった二進法もライプニッツに負うことは周知の如くであって、これを想起するだけで十分であろう。西田幾多郎先生も晩年に「いままで自分の思想はヘーゲルに近いと思っていたが、今ではライプニッツだ」と洩らされていた。
◎書評の経験 下村寅太郎(『リテレール』1992 夏No.1〔創刊号〕)
処女作『ライプニッツ』(「西哲叢書」、弘文堂──現在の弘文堂ではない)が出版された時、どんな批評を受けるか、不安と怖れがあった。実際に怖れた。全力を盡くしたと言い切れなかった。準備の方が大きくてそれを使用しきった感じがない。これはその後も自分の癖になった。「癖」で「意志」ではない。日本での最初のライプニッツのモノグラフィでもあり、何よりもライプニッツは「大物」であったから、引け目は如何ともなしがたかった。自分よりも秀れた研究者がある筈であるから、軽蔑されることは必然と思った。読んだ名著や大作が重い負担だった。自分の学識の貧困矮小の実感が重圧した。勿論これは謙遜ではなく圧倒的な実感という外なかった。処女作が模作になることだけは嫌悪した。名作に接したことが激励でもあり圧力でもあった。最も臆病ならしめたものはライプニッツの作品を読み盡くしていないことの自意識であった。これは現在の自分の力にあまるものであって、少々の時間的制限ではない。海外の新しい研究所には屢々「未刊行資料による研究」の銘が標題に記されている。このようなことは固より極東の駆けだしの若僧の克くし得るものではない。結局、せいぜいで出来ることは既製の書とはいささか異なる構成か方法か、新しい問題の提出を試みることである。いかなる名著も時代の解釈の制約がある。少なくとも「現代」の人間である「特権」を仮令一隅に於てでももっている。これを唯一の拠り所とする外ない。固よりこれも若気のいたすところであるが、その「志」だけは恩恵とする外ない。追いつめられた挙句書き始めたが──書き始めると初めて何だか自分なりの形が出来てくる。「弾み」すらつく。この経験はその後いつも経験することになった。そして一応の展望の出来る尾根に立ったような気がする。峠に立って天下を眺望するという爽快な感じがする。しかし常に前方には更に高著が聳えている。それは却って意欲をそそり立てる。この小著が出来たことは、低い峠ながら天下を展望する悦びと鼓舞を経験せしめた。実際にこの経験から引き続いて小冊が流出することになった。
しかしこれは内心の問題で、出版そのものはそれの出現の直後から、書評の期待と怖れが相交錯して湧出したことも事実である。しかし書評らしい書評も出なかった。これは一応安堵でもあったが不満でもあった。かなり時が経った頃、田辺先生から「安部(能成)君からの手紙に君の本の批評が書いてあって『後生畏るべし』とあったよ」と伺った時、正さしく青天の霹靂であった。も一度聞き直そうとする思いを辛うじて抑制した。それに続いて和辻先生へも同じような手紙が来たと伺った。先生たちは皆親切な方々だと心底から感銘を受けた。
その翌年、小さな『自然哲学』(弘文堂)が出来た時、初めて安部先生に献呈本を差し上げた。今度は期待したのだが「今忙しいから何れ後で」との端書が来た。それから二年後、東京に赴任し、安部先生の学校(学習院)にも非常勤講師として勤務し、初めて先生にお目にかかった。その後何かの機会に『ライプニッツ』の批評を頂戴した時の感激と『自然哲学』からの落胆を申し述べたところ、ふたつとも先生の記憶に残っていなかった。先生の多忙と豪胆に改めて感を深くしたのであった。「それは大変失礼なことをした」と詫びられたが。
このような冗舌をするようになったのは、自分も甲羅の生えたことだといささかほろ苦い感じがする。
最後の安部先生の「後生畏るべし」の一件は、逗子で直接うかがった覚えがありますが、後日譚については、この小文で初めて知りました。下村先生にも著作の評判に一喜一憂する日々があったのだと思うと心がなごみます。
今秋より、第I期『ライプニッツ著作集』も品切の巻から順次新装版で復刊予定です。この機会に、第I期の「刊行の辞」も味読いただければ幸いです。
(十川治江)

下村寅太郎先生(1902 – 95)