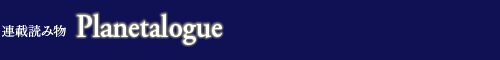第20回 永遠の哲学の息吹
第2巻『法学・神学・歴史学』の第2部「神学」の掉尾を飾るのは、ライプニッツ68歳の誕生日(1714年7月1日)の日付が記された講演草稿『ウィーン講演』(枝村祥平訳・解説)。6月18日付の手紙でゾフィーの訃報を受けて間もない時期の思索の沈潜がうかがえる珠玉の一編です。
アカデミー版収載のさいに予定されているタイトルが、「聖なる哲学の創始者としてのギリシア人について」なので、サブタイトルとして示しています。
『タオ自然学』や『生命潮流』など、科学とスピリチュアリティを架橋しようとする本を翻訳出版してきた工作舎にとって、オルダス・ハクスリーの『永遠の哲学』は、とても気になる一著でした。
「永遠の哲学」という言葉はライプニッツの造語(philosophia perenis)から来ているが、「永遠の哲学」ということ自体は、物と命と心の世界の実体を成す神的な「実在(リアリティ)」を認識する形而上学にせよ、神的な「実在」に似ているか、ひいてはそれと同一の何かを人間の魂の中に見出す心理学にせよ、あらゆる存在に内在すると共にそれを超越している「根拠」を知ることが人間の最終目的であるとする倫理学にせよ、いずれも記憶を超えた遠い昔からあった普遍的なものなのだ(『永遠の哲学』1944; 中村保男訳、平河出版社 1988)。
このように書名の由来を冒頭にかかげながら、典拠もなく、収載した東西古今の至言のアンソロジーに、スピノザは含まれていてもライプニッツはひとつもないのです。
オルダス・ハクスリーといえば、かのダーウィンのブルドッグとして名を馳せたトマス・ヘンリー・ハクスリーの孫、進化の総合説を主導したジュリアン・ハクスリーの弟という英国の知性を代表する家門の出。『すばらしき新世界』(1932)でテクノロジーに管理されたディストピアを描いて小説家としての地歩を確立した後、カリフォルニアに移住。『永遠の哲学』のテクスト逍遙からさらに歩を進めて、自らのメスカリン体験を記した『知覚の扉』(1954)を公刊して、ハーヴァード大学で幻覚剤研究をしたティモシー・リアリーや隔離タンクによる感覚遮断実験で知られるジョン・C・リリーに多大な影響を与えました。
ライプニッツと「永遠の哲学」を関連づけることじたいに問題はないものの、彼の造語ではないことを明らかにしたのは、ルネサンス研究者チャールズ・B・シュミットが『観念史ジャーナル』27(1966)に寄稿した「アゴスティノからライプニッツにいたる永遠の哲学」でした(坂本邦暢氏のブログ参照)。
この論考においてシュミットは、「永遠の哲学」という言葉の初出は、反プロテスタントの急先鋒だった司教座聖堂参事会員にしてヴァティカン図書館司書アゴスティノ・ステウコの著書のタイトル、『永遠の哲学』(De philospphia perenii, 1540)であったとし、同書を読んで内容に共感していたライプニッツは、古代よりつづく叡智の伝統を「永遠の哲学」と呼んだのだとしたのです。
アカデミー版の編集者が『ウィーン講演』に付したタイトル「聖なる哲学」の内実は、地域性・文化性の違いや時間の変化を超えて存続する知恵、まさしく「永遠の哲学」にほかなりませんが、『ウィーン講演』のテクストの中にこの言葉はありません。
ライプニッツによる「永遠の哲学」の使用例は、『ウィーン講演』の翌月、8月26日付のニコラ・レモン宛の手紙にあります。
もし閑があったら私は自分の説を古人の説や他のすぐれた人々の説と比較して見たいと思っている。真理というものは人が思っているよりも方々に行き渡っているものである。ただその色が褪せていることがよくあるし、また何かに覆われたり微かになったりちぎれちぎれになったり余計なものが付加わってそこなわれ、役に立たなくなっていることも非常に多い。古人もしくは(もっと一般的に言って)先人についてもそういう真理の跡を見出せば、泥から黄金を、石からダイヤモンドを、暗から光を得ることになる。それこそ「永遠に続く哲学」(perennis quædam philisophia)である(河野与一訳『単子論』解説、岩波文庫 1951;現代かなづかいに改変)。
ニコラ・レモンは、ゾフィーのもとで幼少期を過ごしたエリザベト・シャルロッテが嫁いだオルレアン公フィリップの重臣(「通信」第8回)。『弁神論』(第I期第6・7巻)を読んだニコラ・レモンが、ライプニッツに熱烈な賛辞を書き送ったことをきっかけに、前年(1713)から文通が始まっていたのでした。上に引用した手紙には、三代の神聖ローマ皇帝に仕えた元帥オイゲン公のためにウィーンで書いて献呈した『理性に基づく自然と恩寵の原理』(第I期第9巻)の写しも添えられていたそうです。
ニコラ・レモンと彼の周りの教養人のために綴った『モナドロジー』(同前)は、同時期に何度も推敲を重ねて仕上げられました。
『ウィーン講演』、『理性に基づく自然と恩寵の原理』、『モナドロジー』の3編を併せ読むと、ゾフィー・シャルロッテに続いてゾフィーにまで先立たれたライプニッツが、自らを奮い立たせて悲嘆の土壌のうえに静謐な調和の境地を拓いていったプロセスをたどる心地がします。
『ライプニッツの哲学』(1900)を著したバートランド・ラッセルとも親交のあったオルダス・ハクスリーが、ライプニッツのテクストを読んでいても不思議はありませんが、果たしてどのテクストをどの程度読んでいたのか、あるいは2次文献により共感したのか、今のところ明らかではありません。
いずれにせよ、「私」とか「私の」という言語の使用による現代人の勘違いを指摘するハクスリーの問題意識は、『ウィーン講演』の時期に「モナドの哲学」を2編のテクストとしてまとめたライプニッツに通じるものがあります。
僧が自分のことを「私」ではなく「この罪深い者」とか「この無用な僕」と呼んでいると、自分の「まとまりがなく分離した」自己性を当然視することがなくなって、神や隣人との真実な有機的関係に気づくようになるのである(『永遠の哲学』同前)。
『永遠の哲学』で最も引用されたのは、ハクスリーが「英語の散文の唯一の名人であったうえに当時の最も興味のつきない思想家」と評する、ウィリアム・ロー(1686-1761)の言葉でした。ローは、ハクスリーの時代も今も知る人ぞ知るといった類いの人物ですが、ライプニッツをハノーファーに残してイングランド国王となったジョージ一世(ゲオルク・ルートヴィヒ)に対する忠誠の誓いを拒んだために、英国国教会で聖職につくことを禁じられた反骨の聖者でもありました。
(十川治江)

カウンターカルチャーに多大な影響を及ぼしたオルダス・ハクスリー(1894 – 1963)