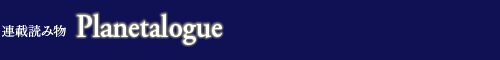第25回 生ける印刷術
意味のある偶然の一致。ユングとパウリが名づけた「シンクロニシティ」は、古来、虫の知らせとか天の配剤とか表現されてきた一種の奇瑞現象。ライプニッツ著作集の第II期をスタートさせて以来、悦ばしいシンクロニシティが相次いで起こっています。
第2巻『法学・神学・歴史学』を刊行したさい(2016. 10)、月曜社の小林浩さんは、「ウラゲツブログ」で同月に刊行されたコメニウス・セレクションの第3弾『覚醒から光へ──学問、宗教、政治の改善』(太田浩一訳、東信堂)と並べて「より良い世界の建設をめぐるコメニウス(1592 – 1670)とライプニッツ(1646 – 1716)の新刊が立て続けに刊行されたことは非常に印象的です」と紹介くださいました。
コメニウス『地上の迷宮と心の楽園』(相馬伸一監修・藤田輝夫訳 2006)、『パンパイデイア』(太田浩一訳 2015)の二冊がすでに東信堂から刊行されていることも、同ブログで遅まきながら知ることができました。
今年4月には、コメニウスの全容を濃縮して紹介した相馬伸一『ヨハネス・コメニウス 氾知学の光』(講談社選書メチエ)が刊行されました。早々と読売新聞に納富信留氏による書評も掲載され、「本書を道案内に彼と共に遍歴する知の旅に出よう」と推奨されました。
同書は、宗教対立の坩堝にあったチェコに生まれ、30年戦争の混乱にもまれながらも、ヤン・フスの流れをくみながら非暴力主義をつらぬくチェコ兄弟教団の牧師として、氾知学(パンソフィア)を軸に、学問(教育)、宗教、政治の理想を追いつづけたコメニウスの姿を激動する時代背景とともに活写しています。
相馬氏はコメニウスに取組んで四半世紀、15年にわたって論考を発表してきた方。チェコ文学の古典とされる小説『地上の迷宮と心の楽園』から教育論『大教授学』、百科全書的入門書『世界図絵』にいたるまで、「セレクション」を編むほど膨大なコメニウスの著書の要点にスポットを当てつつ、コメニウスの内面に迫ります。
『大教授学』には、思慮深さを養うための指導法として「生ける印刷術」という比喩が用いられ、誤解も招いてきたとのこと。コメニウスの主旨は、印刷とは世界からの一方的な刻印(インプレス)ではなく、世界への刻印(エクスプレス)でもあるという点にあったと相馬氏は指摘しています。
デジタル化がすすみ、あらゆる情報がウェブ上で得られるようになって印刷物がどんどん衰退しつつある昨今、教育界や出版界に身をおく立場になくとも、「生ける印刷術」は、認識と表現の本質をついた比喩として、後世に渡したいキーワードです。
コメニウス50歳のとき、46歳のデカルトとオランダで会って4時間話したそうです。別れぎわにデカルトは「私は哲学を越えてはいかない。だから、私に残るのはあなたが扱われる全体の部分にすぎません」と励ましてくれたとコメニウスは回想しています。ところが21世紀になって、ハーグの公文書館で発見されたデカルトの友人の医師ヴァン・ホーヘランデ宛の書簡で、デカルトがパンソフィアには批判的で、新しい発見について論証すべきと評していたことが明らかになりました。
このデカルトの1638年8月26日付ホーヘランデ宛書簡は、山田弘明先生がプロジェクト・リーダーとして上梓した『デカルト全書簡集』全8巻の第3巻(安西なつめ訳、知泉書館 2015)で、日本語で読むことができます。
コメニウスは故国を追われ、遍歴の生涯を送ることになりましたが、ハイデルベルク大学在学中にフリードリヒ5世とイングランド王ジェームズ1世の娘エリザベスの豪華な婚礼に居合わせており、プロテスタント勢力結集の象徴としてのこの一族への思いは、ライプニッツ同様ひときわ強かったと推測されます。
ゾフィーの姉、エリザベス、ルイーゼ・ホランディーネにつぐ三女ヘンリエッタが嫁いだトランシルヴァニア公ジェルジ2世の弟ジクムントに、コメニウスは『ダビデに対するナタンの秘話』と題した著作を献呈して奮起をうながしています。
またイングランド在住のサミュエル・ハートリブと親しく交わり、のちに王立協会の柱ともなる知的サークルを共にしたコメニウスの姿は、王立協会の事務局長オルデンバーグと交流したライプニッツと重なってきます。
チェコスロヴァキア共和国初代大統領マサリクが評したように、コメニウスの氾知学はライプニッツによって、ひろく後世にまで伝えられることになった面もあるでしょう。
ゾフィ・シャルロッテが嫁いだベルリン宮廷の廷吏として、教会合同やアカデミー建設をめぐってライプニッツと協議したダニエル・ヤブロンスキーが、コメニウスの二番目の妻との間の次女の息子、つまりコメニウスの孫であったことも、相馬氏の本で初めて知りました。ヤブロンスキーは晩年、ライプニッツが創設し初代会長に就いたベルリン諸学アカデミーの会長にも就くことになります。
相馬氏の本の第一章「地上の迷宮」の扉には、アルフォンス・ミュシャ(ムハ)のスラヴ叙事詩に描かれた晩年の諦観ただようコメニウスが掲載されています。
折しも3月8日から6月5日まで国立新美術館で開催されていたミュシャ展は、スラヴ叙事詩20作が本邦初公開とあって、連日伝えられてくる混雑ぶりにひるんだまま、見る機会を逃してしまいました。
相馬氏の本の扉は白黒なので、中央のカンテラの光を見分けにくいのですが、ウェブ上のカラー画像から、荒涼とした世界がひろがっているようでも、地上の迷宮を照らす光が消えはしないことを示したミュシャのコメニウスへの深い共感もうかがえます。
スラヴ叙事詩には、コメニウスの属したチェコ兄弟教団の教義を確立したペトル・ヘルチツキー(1390 – 1460)を描いた一枚もあり、ミュシャのスラヴ精神史へのひとかたならぬ思いを汲み取ることができます。
工作舎のHPでも告知したとおり、ミュシャ展が閉じてまもない6月20日から、上野・西洋美術館でアルチンボルド展がはじまりました。同じチェコでも今度はハプスブルク家、カトリック側の文化遺産の公開です。
プラハのルドルフ2世の宮廷が宗教的に寛容であったおかげで、諸技芸の花が咲き誇り、ルター派のヨハネス・ケプラーはティコ・ブラーエと出会えて、『新天文学』を世に送りだすことができたのでした。
来年1月からは、「ルドルフ2世の驚異の世界展」もBunkamura ザ・ミュージアムで開催されます。こちらのテーマはずばり驚異の部屋。ライプニッツが普遍学の出発点に位置づけた現物陳列室です。
それまでには第3巻『技術・医学・社会システム』も書店の棚に陳列したいと願ってはいますが、刊行時期の公開には今少し猶予をいただきたいというのが実状です
(十川治江)

アルフォンス・ミュシャ(ムハ) スラヴ叙事詩 コメニウスの最後の日々