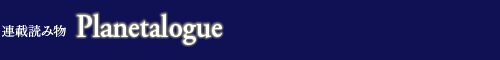第33回 私をみがく道具立てとしての省察
第II期第2巻・第3巻をつらぬくキーワードのひとつに「実践を伴う理論」(Teoria cum praxi)があります。大学ではなく宮廷を職場としたライプニッツにとって、理論的探究と実世界をより良い方向へ導くための実践は、不可分の営みでした。
外交使節団の一員として、26歳から30歳まで過ごしたパリで多彩な人士に出会って吸収した知識とさまざまな現場で体験した事象は、ライプニッツのこのモットーを強靭なものとしたことでしょう。この時期にホイヘンスを介してデカルトの代数幾何学を知り、たちまち微積分学を創始した快挙 (第I期第2巻)は、後世に物理現象を解読して技術的開発をうながす強力な手段を提供することになりました。数学への集中ぶりは、相当なものであったろうと思われますが、決して他ジャンルへの関与を閉ざしてはいません。
悪の存在をめぐる「第一の弁神論」とも称される『哲学者の告白』(清水洋貴・長綱啓典訳; 第II期第2巻第2部1)をまとめ、博覧会企画『奇想百科』(佐々木能章訳; 第3巻第1部1)を起草し、ゼンマイ時計の改良案『懐中時計の精度』(稲岡大志訳; 第3巻第1部2-1)を論じています。さらに論文にするのは後年になりますが、先進国フランスの時計職人との出会いにより、ドイツ時代に考案していた計算機の歯車を改良し、ロンドン王立協会とパリ諸学アカデミーで公開し、後者からは3台の受注に成功しています(稲岡大志訳『計算機の発明』第3巻第1部4解説参照)。
そんな多忙で幸福なパリの日々の終ろうとするころ、小論ながらライプニッツのモットーの原点ともいうべき論考『省察の使用について』(津崎良典訳; 第3巻第3部3) が記されました。
ライプニッツは「省察とは、自分が何であるのか、自分がどうなるのかについて、全般的な考察を加えること」と定義して論考を進めます。
パリに着いた年(1672)の暮に無類の理解者ボイネブルク男爵を喪い、翌年2月には主君のマインツ選帝侯・ヨハン・フィリップ・フォン・シェーンボルンの訃報に接して身分が不安定になっていたライプニッツは、パリでの最終年(1676)初頭、ハノーファーの宮廷顧問官としての招請状に受諾する旨の返事を送っていました。
『省察の使用について』は、新たな環境に身を置くにあたって、後悔しない人生をおくるための道具立てをととのえ、順序立てて自らに課すためのレジュメでした。
意表をつくのは、歴史に名を残すほどの数学的業績をあげたライプニッツが、省察のための練習問題として数学に取り組むよう推奨していることです。数学なら間違いを犯しても危険はなく、間違いに気づくのも困難ではないので、いつどこで出会うかもしれない失敗に備えておけというのです。
第1段階の数と線に関する練習からはじめて、第7段階の「深い静寂のうちに」「現生のどの甘美すらも超える満足とともに過ごすことになる」境地まで、自らの生活原則を支える道具立てのパースペクティブを記したのでした。
この論考の重要性を指摘されたのは、2015年、第7回日本ライプニッツ協会大会の特別講演者として来日し、筑波大学東京キャンパスでも「ライプニッツの〈省察〉について」と題して講演したポール・ラトー氏でした。
同講演でラトー氏は、省察(méditation: 瞑想)をキリストと対話するための宗教的修練から、真理にいたるための哲学的修練へと転換したのはデカルトであり、さらにライプニッツは正当な推論を可能にするための実践的な道具立てとして省察を位置づけたと明快に示されました。
ラトー氏の日本ライプニッツ協会における特別講演においても、筑波大学の講演においても通訳をつとめ、『省察の使用について』を訳出して精緻な訳注・解説を記した津崎良典氏初の単著『デカルトの憂鬱:マイナスの感情を確実に乗り越える方法』(扶桑社)が、新年早々刊行されました。01デカルトはいつも「方法に従う」から21デカルトは「三叉路で迷う」まで、日常生活で誰でも大なり小なり経験する動詞の切口により、デカルト哲学の醍醐味を伝える実践的ガイドとしています。
憂鬱症に悩むエリザベト宛の書簡ではじまっていることに象徴されているように、同書には要所にゾフィーの長姉・エリザベト宛のデカルトの書簡が引用されています。読み進むうちに、読者はデカルト=エリザベトの親密空間にそのままワープして、著者に憑依したデカルトが私の憂鬱を癒そうと意をつくしてくれているかのような心地がしてきます。ライプニッツほど現世での実践に重きをおかなかったデカルトですが、エリザベトに対しては、甲斐甲斐しく役に立つ助言を重ねたようすが彷彿としてきます。この感覚は読者が男性であっても享受できることでしょう。
デカルトにもライプニッツにも精通した津崎氏により、世界から孤立して生きようとするデカルトではなく、大切な人の役に立とうと尽力するデカルト像が、みごとに甦りました。
(十川治江)

デカルトと文通しはじめたころのエリザベト(G・ホントホルスト画)